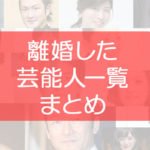多くは子供の戸籍は元夫の戸籍に残ったままですが・・・
離婚時、母親の立場とすると、離婚届けが無事に受理されたとしても子供の戸籍は元夫の戸籍に残ったままです。
そのため、子供の苗字は元夫の姓となりますので、離婚後、子供を自分の戸籍に入れるためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申し立て」を申請して、役所に入籍の手続きをする必要があります。
まず、子供を入籍させるための自分の新しい戸籍を作る
ただ、離婚届けと同時に入籍手続きをすることはできず、まず、子供を入籍させるための自分の新しい戸籍を作ることになります。
ただ、新しい戸籍を作るといっても手続きは特に必要なく、離婚届けに記入した戸籍・本籍に自動的に新戸籍が作成されています。
その後、「子の氏の変更許可の申し立て」に必要な書類等を揃えて、家庭裁判所に申請するようになります。
必要な書類等の主なものとしては、郵便切手、収入印紙、申立書、自分の戸籍謄本、子供の戸籍謄本があります。
また、氏の変更申立人は子供であるため、申立書は基本的に子供が記入するようになります。
ただし、子供が15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人が申し立てすることができるので、親権者等が記入します。
子供が15歳以上のときは子供本人が申し立てることになるため、子供本人による記入が必須となります。
また、子供が15歳未満の場合は親権者のみで手続きができますが、子供が15歳以上の場合は、子供本人が直接家庭裁判所に行って手続きをする必要がありますので注意が必要です。
このように「子の氏の変更許可の申し立て」を申請した後、家庭裁判所において許可審判が行われます。
この許可審判が行われるまでの期間については、家庭裁判所によっても違いがあるようです。
もし、早く結果が欲しいという場合には、直接家庭裁判所で申請手続きを行い、即日審判手続きを行のが良いでしょう。
この許可審判が終われば、家庭裁判所から「審判書謄本」が届きます。
この「審判書謄本」と離婚届けを提出した際に渡された「入籍届け」を役所に提出すれば、これで子供を自分の戸籍に移動して名字を変更することが可能となります。
このように、子供の戸籍移動の手続き自体は簡単であり、家庭裁判所での離婚に伴う氏の変更手続きであることから、よほどの不備がない限り申請は許可されます。
そのため、安心して手続きするようにしましょう。
補足として、戸籍は夫婦および夫婦と氏を同じにする子供ごとに作られると、戸籍法6条に定められています。
したがって、親が復籍した戸籍の筆頭者が、子供にとっては祖父・祖母であるその親の両親であると、親、子供、孫の三世代の戸籍となってしまいます。
これは、戸籍法に反する事態となってしまうため、親が婚姻前の戸籍に復籍した場合で、親がその戸籍の筆頭者ではない場合には、子供がその氏を変更したとしても、その戸籍に入ることはできないのです。
そのため、前述のような、子供の親を筆頭者とする新しい戸籍が作られることとなるので、子供の名字を変更する際には、その子供をその新戸籍に入れる手続きが必要となるのです。
離婚によって子供の親権者の名字が旧姓に戻っても子供の氏は変更されません。
また、前述の通り、父母が離婚しても子供の氏は変更されないため、離婚によって子供の親権者の名字が旧姓に戻っても子供の氏は変更されません。
そのため、母親が親権者の場合で、離婚によって母親の名字が旧姓に戻った場合、親権者の母親と子供の氏が異なるということになります。
この子供の氏を同じくするため、前述のような「子の氏の変更許可の申し立て」を行うわけですが、その一方で、婚氏続称の届け出を出すという母親もいると思います。
この場合、離婚しても母親の姓は旧姓には戻らず、婚姻中の姓を引き継ぐことになります。
ただ、「婚姻中の氏」と「続称の手続をとった氏」は法律上では、別の氏とされます。
したがって、呼び方は同じであってもその親と子の氏は異なることとなり、法律上は別の氏として扱われることになりますので注意しましょう。